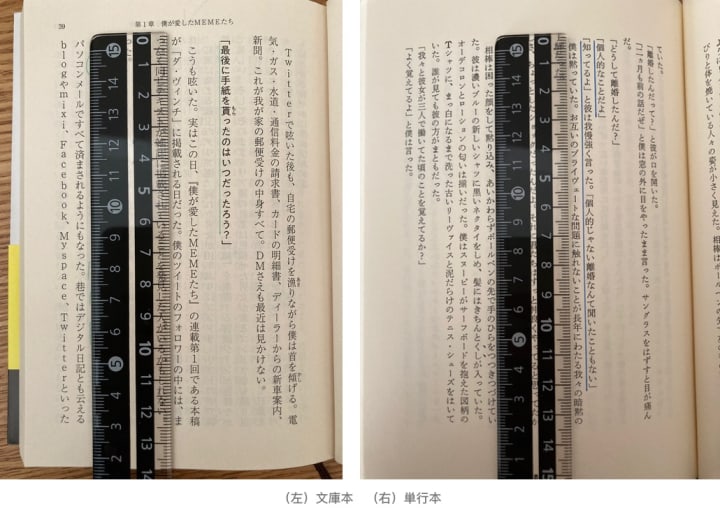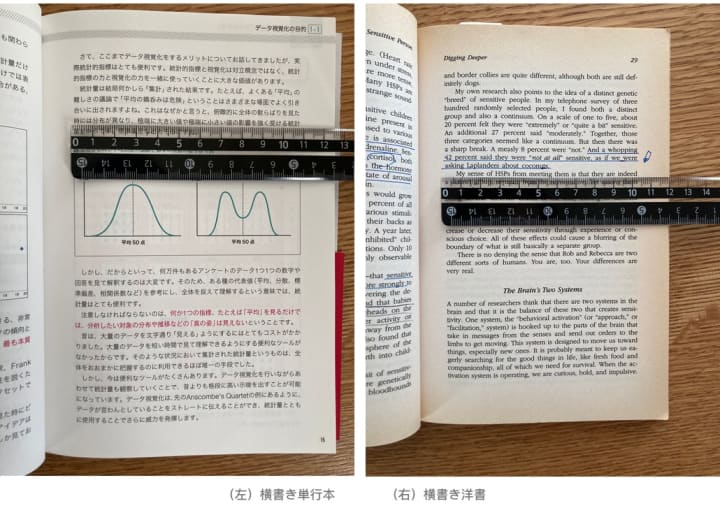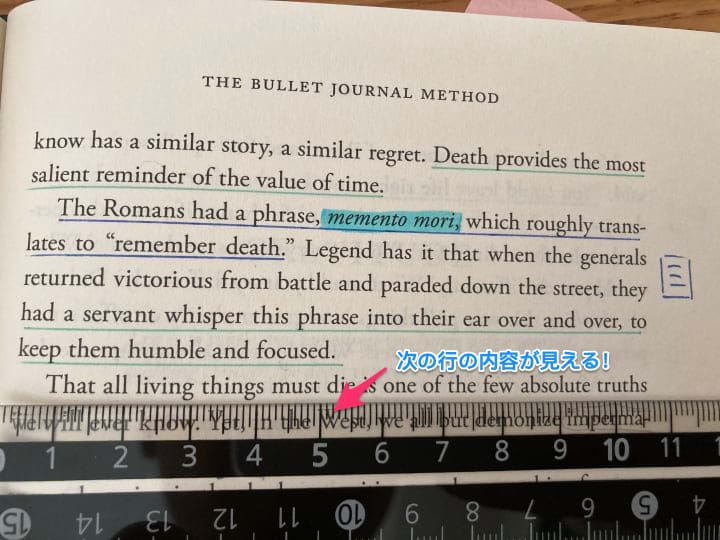いつも同じ男に痛めつけられている。
一週間や二週間に一回の頻度で。悲惨な状況である。よだれを垂らしながら、間抜けな顔にさせられ、血まみれになったり、頬が腫れたりして。
そうです、ご想像のどおり歯医者のことです。これが僕にとっての「身近な恥辱」である。
関連するテーマで、床屋で髪を洗われることがもっとも恥辱だと、村上春樹は『やがて哀しき外国語』で訴えた。
「だいたい頭を後ろにそらせて髪を洗うなんていうことは、人間性に対する大いなる侮辱であるように僕は感じてきた。だって髪を洗われているときの人間の顔なんてぜったいに馬鹿みたいなものだし、そんなものを上向きに世間に晒すのは、恥辱以外のなにものでもないじゃないですか。」(「運動靴をはいて床屋に行こう」節より)
うん、想像はつく。でも今の美容室ではフェイスガーゼを顔に覆うから、最低限の尊厳性は保たれると思う。しかし歯医者となればそうはいかない。映画で怪我の緊急処置をされる場合、主人公が口にタオルを入れて、それをしっかり噛みながら痛みに耐えたりするよね。歯医者にはこれは通じない、だって口を開けとかないといけないから…
虫歯の治療で型取りするときの話。僕は座った姿勢で口を大きく開け、よくは見えなかったけど担当の先生は「銃」のような機械を持ち、引き金を繰り返し押しながら、液体とも固体とも言いがたいドロドロの物体を僕の口の中に発砲した。そして数分間その体勢を維持してと命じられた。嘔吐反射を必死に堪えながら、だんだんこれが学園ドラマに出てくるいじめのシーンとも似ているなと思い始めた。先生が戻ってきたとき、僕の口の中のよだれは噴火寸前の状況までこみ上げてきた。歯の形がくっきりと取られたであろう物体が取り出された際、どんな堤防も防ぐことのできないよだれが一気に流れ出て、宙に太くて粘着な線を引きながら舞い落ちる…
これ以上の恥辱があるだろうか。
まだ男性の先生でよかった、ほんとに。一般的に、男は白衣の異性の先生や看護師に惹かれる傾向があるようだが、僕にとっては何があっても女性の歯医者に恋心はぜったい抱くことはない。こんな醜態を晒した後にどんな顔でデートに誘うっていうのか…
これは僕が歯の定期検診を怠慢したから、そのつけが回ってきたと言いようがない。自業自得そのもの。
そういえば僕の両親も歯の状態がよくない。お二人の歯医者に行く話は昔からしょっちゅう聞く。当時は「神経を抜いた」、「被せもの」などの用語は理解できず、僕は特に問題視しなかったが、今思えば両親と似たような治療を受けているなと気づく。家庭環境が子供に与える影響という面で考えてると、こんな展開は意外でもない。
もちろん、親に責任転嫁するつもりは毛頭ない。もしかすると、これは僕の家庭だけの問題ではなく、僕の生まれ育った中国の当時の公衆衛生知識の欠如に由来するかもしれない。それについて少し語ろう。
僕が中国を出た二十三歳までは、歯の定期検診なんて言葉すら聞いたことがなかった。両親からも、周りの同世代の友人からもそんな話はまず聞かない。また、鮮明に覚えているのが、小さいときに「デンタルフロスと歯間ブラシは、歯と歯の隙間を開けてしまうからやっちゃだめ」という誤った情報を大人たちから教わった。
日本に来て数年経った頃に、奥歯が急に激痛を起こした。歯医者には行かず、痛み止めを飲まず、そのまま耐久しながら普通に仕事をこなしていった。一週間くらい続いて、あまりの痛みで舌でその奥歯を何度も何度もなめていたら歯が取れてしまった。親知らずだから、自然に取れる場合もあるだろう。しかしなんでそこまで愚直に歯医者、あるいは医療を受けることを拒んでいたのかは、今になっては恥ずかしいとしか思えない。
歯に限らず、医療そのものについての国民的意識にも問題があったように思う。我慢するのが美徳で、よっぽどの病気がない限り病院は避けるという風習。自己判断で薬を調達するのが当たり前。医療保険とか、医療費がどうだったとかは、当時まだ子供の自分にはよくわからなかったけれど、大人たちの会話からよく聞くのは、裏で賄賂をしとかないとちゃんと診てくれないとか、大した病気もないのにあれこれ検査させられ、医療費が膨らんだとか、そんな話ばかり。
僕の中国の友人から聞いた話は更に驚く。彼女はお母さんの病気を診てもらうために一緒に北京の病院を訪れた。葛藤しながらも主治医に札束が入った封筒を渡した。その先生はただ黙って素早くそれを受け取った。その瞬間、「あ、こうやって自分は大人になったな」と実感したと語った。まだ少女だった友人がそんな思いをしなくちゃいけないなんて、胸が張り裂けそうになる。
中国はとても大きい国でいろんなことは一概には言えない。これはあくまで当時の僕と僕の周りの人たちを取り囲む環境から見えてくる定期検診への抵抗、医療機関への不信、公衆衛生などの問題であろう。そしてこれらが発展途上国と先進国の絶対的な差だなと痛感した。高層ビルなど数年もあればいくらでも建てられるけど、国民の医療への意識と信頼を変えるのは一世代の時間がかかるかもしれない。それも痛みの時間。
だいぶ飛躍した話をしてしまった。
余談ですが、先日の治レーザービームに照射された。口の中が焼き焦げた匂いがした。そして、今週も同じ男に痛めつけられるでしょう。
(本当は先生にちゃんと感謝してますよ; 頼りにしてます!)